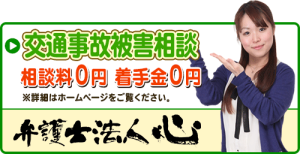精神障害における障害の程度の判定方法
弁護士法人心岐阜事務所ができてから10年以上経過し、多くの方の対応をさせていただきました。
また、最近では、口コミにて100件を超えるご意見・ご感想をいただくことができました。
今後も、弁護士として多くの方のお役に立てるよう努めていきたいと思います。
本日は、精神障害における障害の程度の判定方法について、お話しします。
この点、公表されている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が参考になります。
障害の程度の認定については、ガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考としつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判断するとされています。
このうち、「障害等級の目安」は、基本的に、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の評価の平均を踏まえ、目安表に照らして確認することができます。
日常生活能力の判定は、①「適切な食事」、②「身辺の清潔保持」、③「金銭管理と買い物」、④「通院と服薬」、⑤「他人との意思伝達および対人関係」、⑥「身辺の安全保持および危機対応」、⑦「社会性」といった7項目について、単身で生活している(と仮定した)場合を前提に、「できる」、「自発的にできるが時には助言を必要とする」、「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」、「助言や指導をしてもできない若しくはやらない」の4段階で評価します。
「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」ともに診断書上の項目であり、医師が記載するものです。
したがって、医師に対して診断書の作成を依頼をする場合には、あらかじめ、日常生活における具体的支障何用をしっかりと伝えておく必要があります。
また、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」も重要です。
例えば、就労系福祉サービス(就労支援施設A型やB型)や障害者雇用における就労の場合に、どのように考慮されるかなど記載されています。
精神障害の障害年金の請求では準備・確認すべき事柄が少なくありません。
障害年金の請求をお考えの場合には、弁護士や社会保険労務士へのご相談をおすすめします。